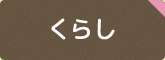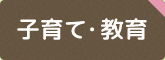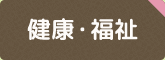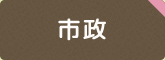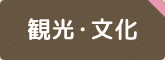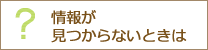子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)予防接種について
更新日:2025年12月1日
平成25年4月1日より、子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種が定期予防接種になりました。この予防接種は、子宮頸がんから女性の健康を守ることを目的としています。
子宮頸がんは、日本では毎年約11,000人が罹患し、約2,800人が亡くなっています。また、女性特有のがんとしては乳がんに次いで罹患率が高く、特に20代から30代のがんでは1位となっています。たとえ死に至らなくても、子宮摘出となる可能性があり、その場合には妊娠や出産への影響だけではなく、排尿障害などが残ることもあります。
子宮頸がんは、発がん性の高いヒトパピローマウイルス(HPV)が持続感染し、がん化することで発症すると考えられています。HPVの感染は一般的によくあることですが、子宮頸がんになるのは稀です。しかし、どのような人が発症しやすいかが不明であるため、だれでも発症する可能性があるといえます。
子宮頸がんは予防できるがんです。子宮頸がんの予防方法は、
「子宮頸がんワクチンの接種(一次予防)」 「子宮頸がん検診(二次予防)」です。
詳細については、以下リンク先の厚生労働省ホームページもご覧ください。
(令和7年4月追記)HPVワクチン接種の経過措置(一部条件付き延長)について
令和6年夏以降のHPVワクチンの需要増により、予防接種を希望しても受けられなかった方がいる状況等を踏まえ、令和7年3月31日までに1回以上接種をしている方につきましては、全3回の接種を公費で完了できるよう、1年間の経過措置期間が設けられました。該当する方は接種をご検討ください。
対象者
平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性の方で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、1回以上HPVワクチンを接種していて、合計3回接種されていない方
経過措置期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日
子宮頸がんワクチンの積極的勧奨が再開されました
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛等の副反応がワクチン接種後に特異的に見られたことから、平成25年6月以降、同副反応の発生頻度がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、積極的勧奨を控えることとされてきました。しかし、令和3年11月に開催された第72回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和3年度第22回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)において、ワクチンの安全性に特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、令和3年11月26日付け厚生労働省の通知をもって、積極的な勧奨を差し控える状態を解消し、令和4年度より順次、HPVワクチンの個別勧奨を再開することとなりました。
![]() 厚生労働省通知:ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について(外部サイト)
厚生労働省通知:ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について(外部サイト)
定期接種対象者
小学校6年生から高校1年生の女子(標準接種年齢は中学校1年生)
医療機関
接種可能な小金井市内の医療機関一覧は以下のとおりです。
予診票
・令和7年度新たに対象となる方のうち定期接種対象者(平成25年4月2日から平成26年4月1日生まれまでの女性)には令和7年5月16日に予診票を発送しました。
・経過措置対象者(平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性の方で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、1回以上HPVワクチンを接種していて、合計3回接種されていない方)はピンク色の子宮頸がんワクチン予診票を使用して接種を行ってください。
![]() 小金井市子宮頸がん予防ワクチン接種保護者同意書(PDF:196KB)
小金井市子宮頸がん予防ワクチン接種保護者同意書(PDF:196KB)
満16歳未満のお子様が保護者の同伴なしで接種をする際は、保護者の同意書が必要となります。お子様のみでの予防接種を希望される場合には、保護者の方が署名をしてお子様に持たせてください。
子宮頸がんワクチンについて
子宮頸がんワクチンは、子宮頸がんの予防に極めて高い効果が得られます。しかし、感染を予防するものであり、すでに感染したウイルスを排除したり、がん等の進行を抑制する作用はありません。また、子宮頸がんから検出されるウイルスにはいくつもの型があり、ワクチンで予防できない型もあります。ワクチンを接種するだけではなく、子宮がん検診も欠かさず受けることで、子宮頸がんを予防することができます。
子宮頸がんワクチンのリスクと有効性については下記リーフレット等のリンクをご覧ください。
| ワクチンの種類 | 2価 (サーバリックス) |
4価 (ガーダシル) |
9価 (シルガード9) 令和5年4月から公費負担の対象に追加されました。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接種間隔 | 初回、初回から1か月後 初回から6か月後 の 計3回 | 初回、初回から2か月後 初回から6か月後 の 計3回 | 初回、初回から2か月後 初回から6か月後 の 計3回 | ||||
| 効果 (予防できるウイルスの型) |
・HPV16型、18型 | ・HPV16型、18型 ・HPV6型、11型 |
・HPV16型、18型 ・HPV6型、11型 ・HPV31型、33型、45型、52型、58型 |
||||
| 副反応 | 50パーセント以上 | 疼痛、発赤、腫脹、疲労 | 疼痛 | 疼痛 | |||
| 10-50パーセント未満 | かゆみ、腹痛、筋痛、関節痛、頭痛等 | 紅斑、腫脹 | 腫脹、紅斑、頭痛 | ||||
| 1-10パーセント未満 | じんましん、めまい、発熱等 | 頭痛、そう痒感、発熱 | 浮動性めまい、悪心、下痢、そう痒感、発熱、疲労、内出血等 | ||||
| 1パーセント未満 | 知覚異常、感覚鈍麻、全身の脱力 | 下痢、腹痛、四肢痛、筋骨格硬直、硬結、出血、不快感、倦怠感等 | 嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、出血、血腫、倦怠感、硬結等 | ||||
| 頻度不明 | 四肢痛、失神、リンパ節症等 | 失神、嘔吐、関節痛、筋肉痛、疲労等 | 感覚鈍麻、失神、四肢痛等 | ||||
| その他 | 稀に報告される重い副反応として、アナフィラキシー様症状、ギラン・バレー症候群、急性散在性脳脊髄炎等があります。 | ||||||
注記:9価ワクチンの接種回数及び接種間隔については、1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合は、少なくとも5か月以上あけて2回接種
注記:同じ種類のワクチンを接種することを原則としていますが、2価又は4価ワクチンで1・2回目の接種を受けた方が、医師と相談のうえ、残りの回数を9価ワクチンで接種することも可能です。
![]() 小学校6年から高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)(外部サイト)
小学校6年から高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)(外部サイト)
![]() 小学校6年から高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版)(外部サイト)
小学校6年から高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版)(外部サイト)
9価ワクチンについて
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の定期接種およびキャッチアップ接種では、これまで2価(サーバリックス)と4価(ガーダシル)の2種類のワクチンが対象でしたが、令和5年4月1日から9価(シルガード9)が追加されました。
接種スケジュール
・1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合
初回接種から通常6か月(少なくとも5か月)以上の間隔をおいて2回接種
注記:5か月未満で2回目を接種した場合は3回接種(接種間隔は15歳以上と同様)
・1回目の接種を15歳になってから受ける場合
2回目接種は1回目接種後2か月後、3回目接種は1回目接種後6か月後の3回接種
注記:上記の方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回接種を行った後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回
2価または4価ワクチンとの交互接種について
原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談のうえ、途中から9価ワクチンに変更し、残りの接種を完了することも可能です。ただし、2価または4価ワクチンを接種した後に9価ワクチンを接種することに対する効果やリスクについては科学的知見は限定されます。
![]() 9価HPVワクチン接種のお知らせリーフレット(定期接種版)(PDF:790KB)
9価HPVワクチン接種のお知らせリーフレット(定期接種版)(PDF:790KB)
![]() 9価HPVワクチン接種のお知らせリーフレット(キャッチアップ版)(PDF:694KB)
9価HPVワクチン接種のお知らせリーフレット(キャッチアップ版)(PDF:694KB)
接種後の症状に関する相談窓口等について
東京都において、HPVワクチン接種後の症状に関する相談窓口をまとめています。
子宮がん検診を受けましょう
ワクチンによってすべての子宮頸がんを予防することはできません。 20から30代のがんの中で最も多いがんは子宮頸がんですが、これは、子宮がん検診を受ける人が非常に少ないためです。子宮がんは、初期の自覚症状があまりなく、気づいたときには手遅れになっていることが多いがんです。定期的に検診を受けることでがんになる前の段階での診断が可能となりますし、早期発見して治療すれば、ほとんど治癒が望めますので、検診はとても重要です。ワクチンを接種するとともに、20歳を過ぎたらぜひ定期的な検診を受けて下さい。
小金井市の子宮がん検診に関するページです。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合わせ
健康課健康係
住所:〒184-0015 小金井市貫井北町5丁目18番18号 保健センター
電話:042-321-1240
FAX:042-321-6423
メールアドレス:s050499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。